名作誕生の必然と偶然 ~ 東京国立博物館『名作誕生 つながる日本美術』
- K
- 2018年5月21日
- 読了時間: 3分
観たいものが多すぎて、どれを取り、どれを諦めるか、毎週悩んでいるKです。いろいろな情報が入ってくるのは便利でいいのですが、取捨選択を迫られることも増えているのかと思ったりします。

東京国立博物館で開催中の特別展『名作誕生 つながる日本美術』は、なんとかして観たいと思っていた展覧会のひとつ。ちょうど土曜日に東京方面に出かける用事ができたので、開館時間が延長されている(土曜日は21時まで開館!)のを利用して、観てきました。土曜日とはいえ午後からだったので、混み具合はほどほど。ゆっくり楽しめました(^O^)
「美の家系図を見るようです」
とは、ポスターに控えめに記されたキャッチフレーズ。まさにその通りで、古い仏像や仏画に始まり、雪舟の水墨画、若冲の鶴図・鶏図、菱川師宣の『見返り美人図』など、さまざまな名作がどのような流れの中で生まれてきたのか、お手本をもとにどう変遷して「名作」に至ったのがわかる展示になっています。
観ていて強く感じたのは、お手本や文化的な素地があったという必然性であり、そこに画家の情熱や個性という偶然性が触媒となって「名作」と呼ばれる作品が生まれてきたんだろうなということ。まったくのゼロから湧き出てくるものではなく、かといって模倣だけでは受け継ぐ(受け継がれてる)ことにはならないのでしょうね。
ひとつひとつが国宝や重要文化財、それにならぶクラスの作品ばかりで、1点1点を観るだけでも「眼福」なのに、それらを並べて比べられる。展覧会だと1列に並んで、順路に従って観ていくことが多いですが、順路をもどっていったり、展示から離れて全体を俯瞰したり、室内をうろうろする人が多い展覧会でもありました。
多様化する展覧会・多様化する美術の楽しみ方
展覧会と言えば、「なんとか美術館展」のように、名の知れた美術館が持つ名作をハイライトで楽しめるもの(飛行機に乗らなくてもいい)や、「だれだれ展」のように、あるひとりの画家にフォーカスを当て、その画業や人生を一気に追いかけることができるものが一般的。でも最近では、あるテーマを軸に、ワクを越えて美術やアートを楽しむものが増えてきているように思います。

いろいろなジャンルのものが一度に触れられるという点では初心者向けでもあり、意外なつながりや変わった視点によって作品への理解、愛で方が一層深まるという意味では愛好者向けでもある。いろいろな価値観が生まれ、多様化が浸透する中で、今まであったものに新しい切り口を与えていくような、こういう展覧会は今後増えていくんだろうなと思います。その中で、これまであまり知られていなかったもの、新しい視点がどんどん提示されていくと博物館はもっともっと楽しい場所になるような気がしていますし、そのようなことを期待しています。
『名作誕生 つながる日本美術』展は、5月27日(日)まで。上野動物園のパンダのシャンシャンとあわせてぜひ!
だいぶ日が長くなってきましたね。







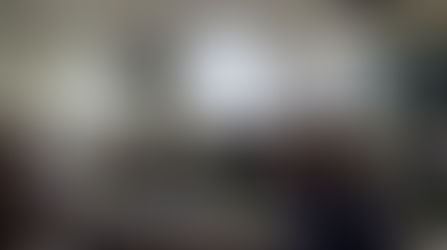











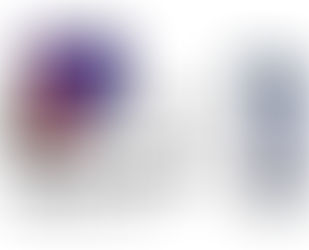


















コメント